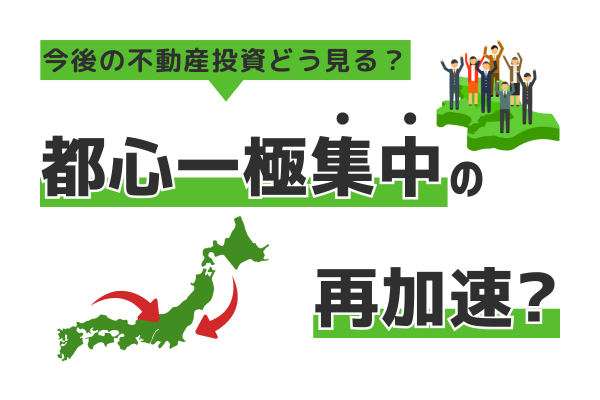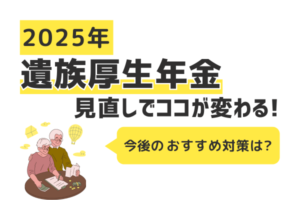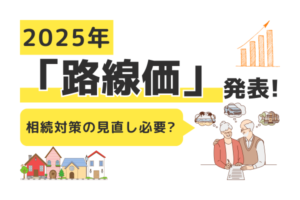不動産投資の成否を決める要素の一つに、「賃貸市場の動向」が挙げられます。
賃貸需要を見極めた不動産投資は、安定した収益を長期的に得ることができます。一方で、空室率が高く収益も不安定な賃貸物件は、損失が大きくなるだけでなく、売却も困難です。
そのため、賃貸不動産投資で成功するには、人やビジネスが集まるエリアの物件に投資することがセオリーとなります。
この記事では、特に人やビジネスの集中が再加速しつつある、都心の動向について詳しく解説していきます。今後の人とビジネスの流れを読み解き、不動産投資にどのような影響があるか見ていきましょう。
加速する首都圏への本社移転
帝国データバンクが9月に公表した『首都圏「本社移転」動向調査(2025年上半期)※』によると、2025年1月~6月までに地方から首都圏に本社移転した企業が200社あり、過去10年で最多となっています。首都圏から転出した企業は150社であるため、全体では50社の転入超過となりました。
加えて、半期で転入超過となったのは2019年以来6年ぶりであり、首都圏エリアの企業吸引力が急回復していることがわかります。
※参考 https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250918-relocation25y1-6/
コロナ禍以降の首都圏の企業動向
2020年以降、企業の動きは脱首都圏に傾いていました。
これは、コロナ禍の影響でビジネススタイルが変化しWeb会議やリモートワークが浸透していったことが、要因の一つとして考えることができます。
また、*BCP対策による拠点の分散化や地方創生への貢献、従業員のワークライフバランスの向上など、地方移転によるメリットが企業経営者の理解を得られた点も大きいとみられていました。
*BCP対策…自然災害やテロ、システムトラブルなどの非常事態が発生した際に、事業を復旧・継続するための計画や対策
首都圏回帰した企業が増加した背景とは
では、なぜ2025年上半期における企業の本社移転が転入超過となったのでしょうか。
現在、コロナ禍の影響が収束しつつあり、再び対面による営業活動が活発になっています。このため、取引の機会を求めて、地方の中小企業が首都圏に本社移転をする動きが目立ってきたのです。
実際に、首都圏への転入元は33都道府県に上っており、地方企業が首都圏に集中する「首都圏一極集中」の動きが強まっています。
首都圏に本社機能があることによる対外的な信用や、ブランド面の優位性が向上している点も見逃せません。首都圏の方が新卒採用などの人材獲得がしやすい点も、地方企業が都心に転入する要因となっていると考えられます。
首都圏への本社移転は今後も増加するとみられており、通年でも5年ぶりに転入超過が見込まれています。そのため、企業の首都圏回帰はさらに加速していくと予想できるでしょう。
大学キャンパスも都心回帰が進む
都心回帰が進んでいるのは、企業だけではありません。2000年代半ばから、多くの大学が都心にキャンパスの移転や学部の集約を行っています。
次は、大学の都心回帰の流れや背景について見ていきましょう。
大学の都心回帰が進んだ流れとは
大学は、2000年代まで都心に既存のキャンパスの拡張を行うことができませんでした。
1959年に制定された「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(通称:工場等制限法)」において、「工場等」に準ずる施設として大学の教室も扱われており、都心でのキャンパス新設・増設が厳しく制限されていたからです。
戦後のベビーブームで学生数の増加が見込まれた際には、都心のキャンパスだけでは対応が難しいと判断され、大学は郊外にキャンパスの移転・拡張を行っていました。
このような流れに変化が起きたのが2002年です。製造業の規制緩和を主な目的として工場等制限法が廃止され、大学は再び都心にキャンパスを拡張することが可能となりました。
まずは、2005年に東洋大学が都心の白山キャンパスに文系学部を集約させました。2013年には青山学院が同様の動きを見せ、2016年には東京理科大学が経営学部を神楽坂キャンパスに移転を行いました。
ほかにも、東京電機大学や桜美林大学、実践女子大学など、2000年代後半から現在に至るまで、多くの大学が都心に学部の移転・集約をしています。
特に、1978年に都心から多摩キャンパスに移転した中央大学法学部が、2023年に45年ぶりに都心にキャンパスを開いた際は、大きな話題になりました。
大学の都心回帰の流れは、現在も続いています。例えば、明治大学では、創立150周年記念事業の一環として、2つの学部を山手線内に位置する駿河台に移転することを発表しています。
今回挙げた大学以外にも、多くの大学が都心へのキャンパス移転や学部の集約を予定しています。そのため、大学の都心回帰の動きはますます進んでいくでしょう。
大学の都心回帰の背景に見える生存競争
こうした大学の都心回帰には、各大学の生存競争が背景にあります。
現在の日本は少子化の影響で18歳人口の減少が続いており、大学は学生数の確保が難しくなってきています。学生数が少なくなると収入源の一つである授業料も減少するため、大学は授業料を値上げする動きを見せています。
しかし、授業料の値上げは、入学希望者数が減少する恐れがあります。定員充足率が一定の基準を下回ると、経常費補助金を減額されてしまうことになるため、大学の経営はさらに苦しくなってしまうでしょう。
そのため、大学は都心にキャンパスを移すことで交通面の利便性を向上させ、通いやすさをメリットに学生数を確保しようとしているのです。
交通面以外にも生活インフラや商業施設が豊富な都心部にキャンパスがあることは、それだけで魅力的となるため、学生や保護者に向けてアピールするブランド戦略にもなります。
都心にキャンパスがあることで、企業と連携して研究を進める「産学連携」が行いやすくなる点も見逃せません。産学連携では、教授や学生が外部組織の研究員との交流で研究を深められるだけでなく、外部から研究資金を得られるようになり、財政的なメリットもあるのです。
学生にとっても大学の都心回帰はメリットが大きい
学生側にとっても、大学が都心にあることで多くのメリットを享受できます。
通いやすさ以外で特に大きいのが、就活の優位性です。都心には多くの企業の本社や支社があり、企業説明会の参加や情報の入手が、郊外の大学と比べると容易になります。
キャンパスと企業との距離も近くなるので、就職活動と授業への参加も並行してしやすくなるでしょう。
就職活動の移動にかかる時間と交通費が少なくなることも、学生にとっては大きな利点と言えます。
都心回帰は自然な流れ?
ここまで、企業と大学における都心回帰の様子を見てきました。しかし、より長期的に都心の動向をみると、都心回帰はビジネスや大学に限った話ではありません。
元々、都心回帰とは1990年代以降に起こった、都心への人口の再流入現象を指していました。
高度経済成長期からバブル期の都心は、地価の上昇に加え大気汚染や騒音公害の影響で居住を敬遠されていました。そのため、都心から郊外へと人口が流出する「ドーナツ化現象」が起こりました。
しかし、バブル景気が崩壊して地価が下落すると、都心の不動産価格が低下して多くのマンションが建設されます。それに伴い、若い世代だけでなく子育てを終えた中高年も、利便性と暮らしやすさを求めて、郊外から都心へと流入する流れが強まりました。これが、本来言われていた都心回帰だったのです。
確かに、企業ではコロナ禍によるリモートワークの推進や拠点分散の成功、大学では学生数の増加と都心のキャンパス拡充の制限など、その時代の状況によって一時的な郊外化があったのは事実です。
とはいえ、都心の利便性の高さと暮らしやすさは、やはり非常に大きい魅力であることは変わりありません。
都心は交通アクセスが良く、商業施設や生活インフラも豊富です。こうした利点は都心の住民だけでなく、既に解説したように企業や大学にとっても様々な面でプラスに働きます。
こうしたことから、時代の状況によって一時的な郊外化はあっても、最終的には都心に人や機能が集中するのが原則なのかもしれません。
今後の不動産投資は、都心を視野に入れた戦略を
少子高齢化による人口減少期は今後も引き続くと考えられており、より「都心フォーカス」が進んでいく可能性が高いです。
実際に、都心の人口は現在も増加し続けており、学生や会社員だけでなく、人材を確保したい企業や大学は都心に機会を求めています。
都心に増加する人口の中心には、ある程度の地位を持つ会社員や高所得者層の親を持つ学生なども含まれるため、今後も高くなる家賃を払える層の増加も期待できるでしょう。また、都心部ではすでに単身者世帯が半数を超えており、企業の社宅やSOHO、セカンドハウスとしての賃貸需要も今後伸び続けると考えられます。
こうした動向を鑑みると、不動産投資で中長期的な戦略を立てるなら、やはり今後は都心一択と言えるかもしれません。