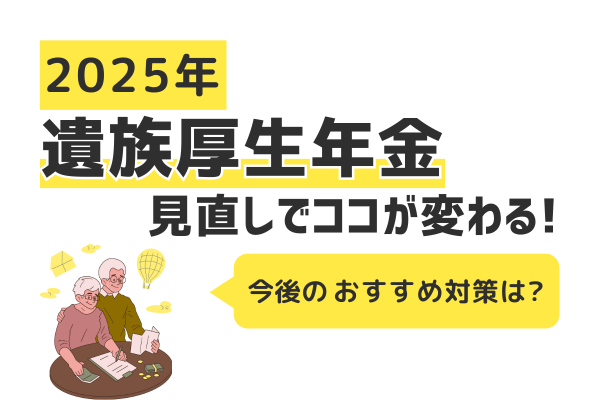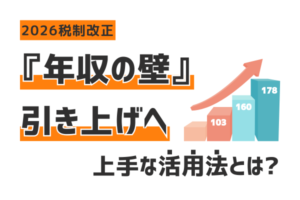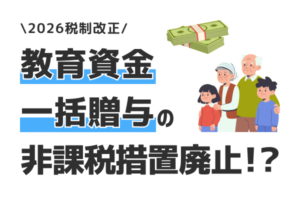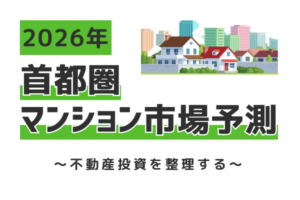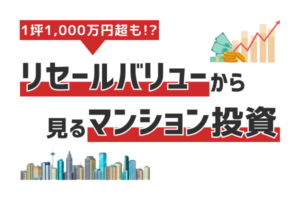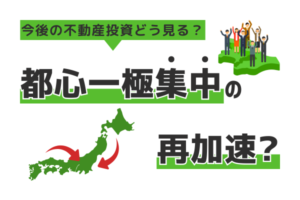2025年6月に年金制度改革法が成立し、2028年以降、私たちの生活に深く関わる年金制度が段階的に変更されることになりました。メディアでは「106万円の壁」の見直しや、基礎年金の水準引き上げに向けた議論などが大きく報じられ、多くの方の関心を集めています。
しかし、これらの改正と並行して、もう一つ重要な見直しが行われることをご存知でしょうか。それが「遺族厚生年金」の制度改正です。
今回の改正が特に焦点を当てているのは、男女間の受給格差の是正です。しかし、それは同時に、万一の際の生活を支える重要な保障のあり方が、根底から変わることを意味しています。
この改正は、すでに年金を受給されている方はもちろん、現役で働く会社員や公務員、そしてそのご家族にとっても決して他人事ではありません。
専業主婦(主夫)のいるご家庭、ご夫婦の年齢が離れている場合、またお子様を育てているご家庭など、実に幅広い世帯に影響が及ぶ可能性があるのです。
本記事では、遺族年金の基本から今回の制度改正のポイント、そして公的制度の変化に左右されないための資産形成術を解説します。
遺族年金とは?
将来の対策を考える上で、まずは現行の遺族年金制度の基本を正しく理解しておくことが不可欠です。
遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族に支給される公的な保障です。
主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類に分けられます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが亡くなった場合に、遺族に支給される年金です。
主な対象は「亡くなった方に生計を維持されていた、18歳年度末までの子ども(または障害等級1級・2級の状態にある20歳未満の子ども)がいる配偶者」または「子ども」となります。
つまり、支給対象となる子どもがいない場合は、原則として受け取ることができません。
遺族厚生年金
一方、遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者(主に会社員や公務員)が亡くなった場合に支給される年金です。
遺族基礎年金との大きな違いは、子どもの有無にかかわらず生計を維持されていた配偶者や親なども対象となり得る点にあります。
支給額は、亡くなった方の厚生年金加入期間やその間の平均標準報酬額に基づいて計算される仕組みです。
遺族年金制度はどう変わる?2025年改正のポイント
今回の年金制度改正において、特に注目すべき遺族厚生年金の見直しは、2028年から段階的に施行される予定です。
ここでは、具体的な変更点と、その背景にある社会の変化について解説します。
遺族年金制度の改正:男女格差の是正と有期給付への変更
今回の改正では、これまで子どもがいないケースで男女間に存在した遺族厚生年金の受給期間の格差が解消され、男女共通の制度へと変わります。
具体的には、60歳未満で死亡した場合、原則「5年間の有期給付」となるのが大きなポイントであり、これは単なる期間の短縮以上の大きな意味を持ちます。
なぜなら、これまで、特に子どものいない妻に対する遺族年金には「生涯にわたる生活保障」というセーフティネットの役割がありました。
しかし、今回の改正で「5年間の有期給付」が原則となったことは、国の保障の役割が「生涯の生活保障」から「自立するまでの移行期間を支える、つなぎの支援」へと、その思想自体が根本的に変わったことを意味するからです。
参考:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
この変化は、特に「万一の際は、生涯の公的保障がある」と漠然と考えていた若い世代の夫婦にとって、ライフプランの前提を根底から見直す必要があることを意味しているのです。
改正の背景:社会構造の変化と男女の平等化
なぜ、このような大きな見直しが行われるのでしょうか。その背景には、日本の社会構造の劇的な変化があります。
かつて主流であった専業主婦世帯は減少し、現在では夫婦共働きが一般的となりました。女性の社会進出が進み、社会全体で男女の平等化が求められる現代において、従来の制度が実情と合わなくなってきたのです。
今回の改正は、こうした共働き世帯の増加や男女の就労形態の多様化といった現代のライフスタイルに制度を適合させ、より公平性を確保しようとする意図があると考えられます。
ライフプランへの影響と見直しの必要性
今回の改正は、特に子どものいない若い世代のご夫婦にとって、これまで「万一の際は生涯の遺族年金がある」と漠然と考えていたライフプランを、根本から揺るがす可能性があります。
ただし、今回の改正には「2028年度時点で40歳以上になる妻」など、現行制度が適用される経過措置も設けられています。まずはご自身の状況が改正の影響を受けるか、冷静に確認することが重要です。
その上で、影響を受けると判明した場合、これは他人事ではありません。公的保障の内容が変わることは、ご自身で準備すべき保障額が変わることを意味します。
「5年間」という有期給付で不足する分は、当然ながら自らで補う必要があります。今回の改正は、現在加入中の生命保険の保障額が本当に十分なのか、今一度見直す絶好の機会と言えるでしょう。
公的年金に頼らない、これからの資産戦略
今回の遺族厚生年金の改正は、公的制度が将来にわたって安泰ではないことを示しています。制度の変化に左右されず自らの手で未来を守るためには、自助努力による資産形成が不可欠です。
では、具体的にどのような手法があるのでしょうか。ここでは代表的なものを比較検討してみましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、自ら掛金を拠出し、運用方法を選んで老後資金を準備する私的年金制度です。最大のメリットは税制優遇にあり、掛金が全額所得控除の対象となるほか、運用益も非課税となります。
ただし、原則として60歳まで資金を引き出すことはできず、あくまで老後資金の確保に特化した制度です。
NISA(少額投資非課税制度)
NISAは、個人の資産形成を支援するための税制優遇制度です。年間投資枠の範囲内で得た金融商品の運用益が非課税になる点が大きなメリットです。
iDeCoと異なり、いつでも資金を引き出すことができるため流動性が高く、ライフイベントに合わせた柔軟な資産形成が可能です。
不動産投資
iDeCoやNISAが、自己資金を元手に資産を「積み上げていく」手法であるのに対し、不動産投資は「万一への保障」と「私的年金」を同時に構築できる合理的な手法です。
不動産投資には、他の金融商品にはない3つの大きなメリットがあります。
団体信用生命保険による「生命保険」機能
ローン契約者に万一の事態があった場合、団信によってローン残債が完済されます。遺された家族には、借金のない収益不動産が残り、安定した家賃収入が生活を支えます。これは、公的年金を補って余りある強力な保障です。
年金のように安定した家賃収入
都心の安定した賃貸需要を背景に、毎月得られる家賃収入は公的年金に上乗せされる「私的年金」となります。自分自身でコントロールできる収入源は、将来の不確実性に対する最高の備えです。
相続や贈与税対策としての有効性
不動産は、現金や有価証券に比べて相続税・贈与税評価額が低くなる傾向があります。特に、賃貸中の不動産はさらに評価額が下がるため、効果的な相続・贈与税対策として活用できます。
このように不動産投資は、単なる資産形成に留まらず、家族の生活を守る保障機能と、老後の安定収入源を同時に確保できる、制度改正の時代にこそ検討すべき有力な選択肢なのです。
まとめ
2028年から段階的に施行される遺族厚生年金制度の見直しは、私たちのライフプランを再考する一つのきっかけです。これを機に、公的制度の役割と限界を正しく認識し、自らの未来を主体的に設計することが重要となります。
たとえ今回の改正がご自身の状況に直接当てはまらなかったとしても、「公的制度は社会の変化に応じて見直される」という事実は、全ての世代にとっての重要な教訓です。将来、いつ、どのような変更があるか予測が難しいからこそ、制度だけに依存しない自分自身の対策を講じておくことが不可欠なのです。
iDeCoやNISAによる積立は有効な手段ですが、それに加え、万一の保障と私的年金を同時に構築できる不動産投資は、変化の時代を生き抜くための極めて強力な一手となるでしょう。
制度改正に一喜一憂することなく、ご自身とご家族の未来を守るための盤石な資産形成を、今から始めてみてはいかがでしょうか。