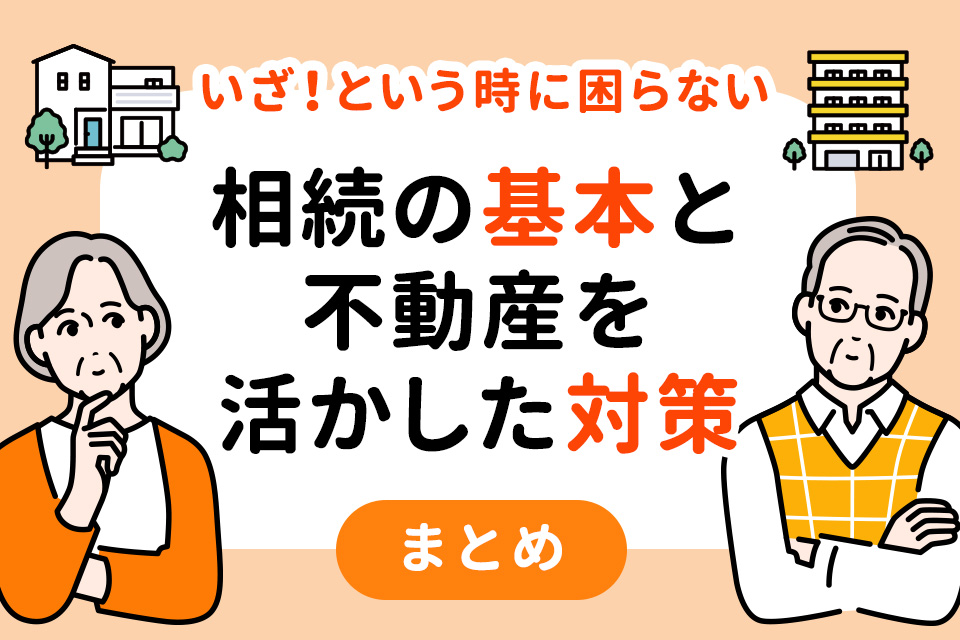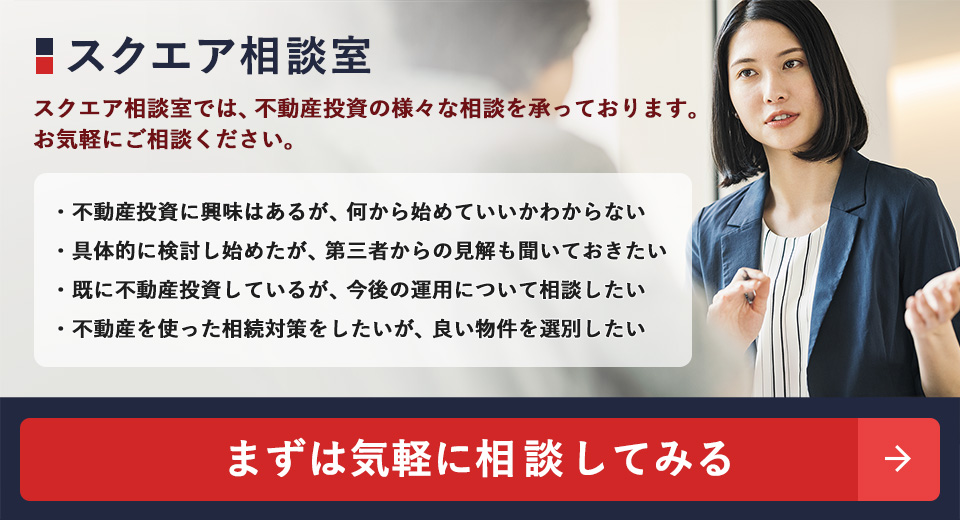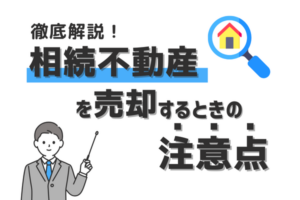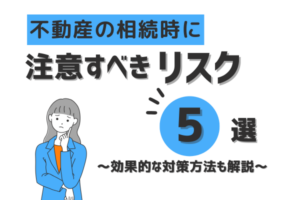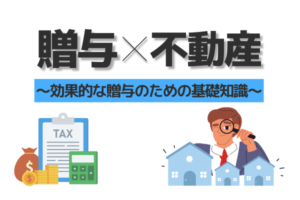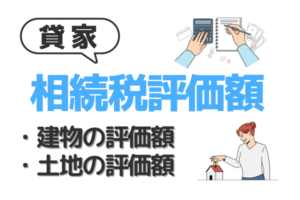ある日突然やってくるかもしれない相続。近年の相続税法改正により課税対象者が増え、これまで相続税とは無縁だと思っていた人も、対策が必要になるケースが増えています。
相続には「相続」と「生前贈与」という選択肢がありますが、それぞれ適したケースが異なります。その判断を左右する大きな要素のひとつが、財産の種類です。特に不動産は、現金とは異なり評価額が抑えられる傾向があるため、相続税の負担を軽減しやすく、相続対策として活用されるケースが多く見られます。
また、不動産を相続する際には、評価額の計算方法や遺産分割の仕方など、知っておくべきポイントがいくつもあります。さらに、相続後のトラブルを避けるためにも、どんな物件が相続に適しているのか事前に検討することも重要です。
本記事では、贈与と相続の違いや不動産の活用方法、手続きの基本までを整理し、スムーズな相続のための知識をわかりやすく解説します。
1.「贈与」と「相続」どちらにすべき?
相続の準備において、特に悩みやすいのが財産分与の方法です。主に「生前贈与」と「相続」の2つに分かれますが、どちらが有利かは財産の種類や適用できる特例によって異なります。
一般的には相続のほうが税負担を抑えやすいケースが多いものの、相続時精算課税制度や各種特例を活用することで、生前贈与のほうが有利になる場合もあります。
生前贈与と相続の違いや、それぞれのメリット・デメリットについては、次の記事で詳しく解説しています。
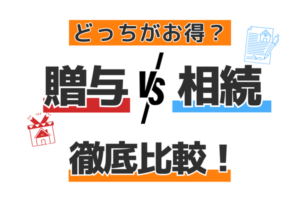
2.相続は現金より不動産がお得?
相続では財産の種類も重要なポイントとなります。同じ資産価値でも、相続方法によって評価額が大きく変わることがあるためです。例えば、現金はそのままの額が課税対象になりますが、不動産は固定資産税評価額や路線価に基づき、相続税評価額が決まります。
不動産は相続時に時価よりも低い額で評価されるうえに、各種特例を活用できるため、相続対策として活用されることが多いです。
次の記事では、現金と不動産の違いや相続税を抑えるための基礎知識について詳しく解説します。

3.賃貸不動産を有効に活かす!相続のポイント
不動産を相続する際は、評価額の計算方法や相続後の家賃収入の扱いなど、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
土地の評価額計算方法:自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
建物の評価額計算方法:固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
また、家賃収入の扱いは「相続開始」と「遺産分割成立」のタイミングで異なり、相続人間でトラブルになることもあります。さらに、共同相続となった場合、管理や売却の意思決定で意見が対立するリスクもあるため、事前の対策が重要です。
不動産の相続税額の計算方法や、より具体的な相続対策のポイントについては、次の記事で詳しく解説しています。
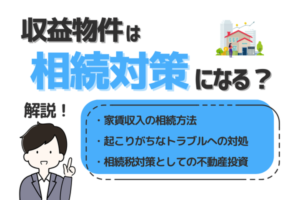
4.区分と一棟、どちらが相続向け?
不動産投資においては「区分」「一棟」が良く比較されますが、相続の面においてもそれぞれメリット・デメリットがあります。すでに保有している物件の種類、相続人の人数や活用方針によって最適な選択肢が異なるため、分割や売却のしやすさを考慮することが重要です。
区分マンションは、所有権を部屋ごとに分けられるため公平に相続しやすく、売却の選択肢も広がる点で有利です。一方、一棟物件は管理を一元化できるメリットがあるものの、分割が難しく、売却先が限られる場合もあります。
相続対策の視点でみた区分・一棟の違いについては、次の記事で詳しく紹介しています。
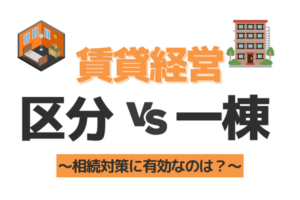
5.相続の基本的な流れ
不動産を活用した相続対策を考えるのも重要ですが、実際に相続が発生した際にはスムーズに手続きを進めることも欠かせません。相続手続きは非常に煩雑で、対応を誤るとトラブルや負担が生じる可能性があります。
特に不動産を相続する場合、相続税の申告・納付は10ヶ月以内、不動産の相続登記は3年以内に行うことが義務化されており、速やかに対応する必要があります。事前に手続きの流れを把握し、必要な準備を整えておくことが大切です。
次の記事では、「親が亡くなったあと」に行う具体的な相続手続きをチェックリスト付きで詳しく解説しています。

6.まとめ
相続はいつ発生するかわからないからこそ、事前の準備が不十分だと手続きの負担が増えるだけでなく、相続税の負担や財産分与のトラブルにつながる可能性があります。特に、不動産を活用した相続対策は、財産の評価額を抑えながら資産を次世代に引き継ぐ有効な手段の一つです。
相続税の計算方法や財産分与のポイントを理解し、どのような形で資産を残すのが最適かを早めに検討することが重要です。また、相続が発生した際には、相続税の申告や登記手続きなど、期限が定められた手続きを適切に進める必要があります。
将来の相続に備え、適切な準備を進めていきましょう。